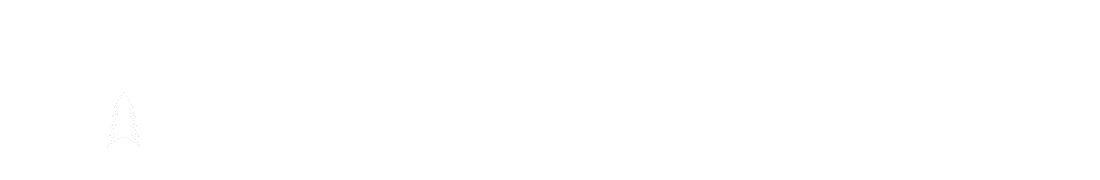白亜紀前期の化石
Fossils from the Lower Cretaceous
恐竜の化石

恐竜(歯)の化石
名前カルノサウルス類?の一種
学名Carnosauria ? gen.et sp. indet.
産地和歌山県有田郡湯浅町
地層湯浅層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
ナイフのような形の歯で、縁に鋸歯がある(ギザギザがある)ことから、肉食恐竜(獣脚類)の歯であることは間違いありません。 ただ、肉食恐竜はどのグループもよく似た形の歯を持っているので、詳しい種類を調べるのは非常に困難です。いくつかの細かい特徴から、第1候補としてカルノサウルス類が挙げられますが、現段階では確実なことは言えません。 なお、恐竜の体長は、歯の化石1本からでも保存の良い同類の化石と比較することによって、おおよその推定は可能です。 特に肉食恐竜の場合、大きな歯の持ち主は体も大きいという傾向がはっきりしています。この化石の場合、歯の大きさ(約2.6cm)から全長は3~4m(尻尾を含む)程度であったと推定されます。
カルノサウルス類って何?
細長い頭骨を持つなどの特徴を持った中型から大型の肉食恐竜の1グループに対する総称で、ジュラ紀中期から白亜紀後期に、世界的に広く分布(オセアニアとインドを除く)していたと考えられています。カルノサウルス類に属する代表的な恐竜としては、アロサウルスやアクロカントサウルス、シンラプトルなどが挙げられます。

恐竜(歯)の化石
名前スピノサウルス類の一種
学名Spinosauridae gen.et sp. indet.
産地和歌山県有田郡湯浅町
地層湯浅層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
寄贈宇都宮聡氏
今回発見された歯化石は、不完全ではあるものの円錐形であったと推測され、表面にはっきりとした縦方向の条線が確認できます。さらに、東京都市大学の中島保寿准教授に電子顕微鏡による断面の微細構造の観察・分析を依頼した結果、歯の表面のエナメル質が厚いことなどの特徴が見られました。これらの特徴の組み合わせは、他の恐竜やワニなどでは確認されておらず、スピノサウルス類でのみ確認されていることから、この化石はスピノサウルス類の歯と同定されました。
スピノサウルス類って何?
獣脚類スピノサウルス科に属する恐竜の総称です。恐竜では珍しく水中で泳ぐことが得意で、主に魚を捕食していたと考えられています。スピノサウルス科にはいくつかの属が含まれますが、特にスピノサウルス属は、体長15mに達する大型恐竜で、背中に帆がある等ユニークな特徴を持つことから恐竜ファンの間でも人気が高く、映画「ジュラシックパーク」シリーズに登場したことでも有名です。スピノサウルス類の化石は、以前は主にアフリカ大陸などで発見されていましたが、近年になってタイ王国などの東南アジアからも多く発見されるようになりました。なお、今回発見された化石については、スピノサウルス類の詳しい種類等は不明です。

画像提供
古生物イラストレーター 川崎悟司氏
甲殻類の化石
名前ホプロパリア・ナツミアエ (ナツミコアカザエビ)
学名Hoploparia natsumiae
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
寄贈熊谷菜津美氏

ホプロパリア1

ホプロパリア2
ホプロパリア属は、現生のアカザエビやロブスターの祖先にあたるエビで、白亜紀前期に出現し、新第三紀に絶滅したと考えられています。白亜紀前期の化石は世界的に見ても少ないので、とても貴重な標本です。ちなみに、種小名のナツミアエは発見者である熊谷菜津美さんの名前に由来します。なお、1つめの写真は頭胸甲と腹部の化石、2つめの写真は鋏脚(ハサミ)の化石です。
アンモナイト

名前シャスティクリオセラス・ニッポニカム
学名Shasticrioceras nipponicum
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
パラクリオセラスと同じようにゆるく巻いた殻を持っていますが、大きなトゲは見あたりません。

名前クリオセラティテス・アジアティカム
学名Crioceratites asiaticum
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
少しほどけてゆるく巻いた殻を持つアンモナイトです。殻の表面にはトゲもあります。アンモナイトの長径は約6㎝です。

名前アナハムリナ属の一種
学名Anahamulina sp.
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
寄贈石橋昻士氏
このアンモナイトの殻はうずまきではなく、ひらがなの「つ」の字のような形をしています。
二枚貝の化石

名前ナノナビス・ヨコヤマイ
学名Nanonavis yokoyamai
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
シコロエガイに近縁な絶滅種です。この標本は殻が溶けた印象化石なので、何も模様がないように見えますが、実は殻の表面にはたくさんの放射状の肋があります。 有田層ではよく見つかる種です。

名前ヒバリガイ属の一種
学名Modiolus sp.
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
ヒバリガイは、料理などに使われるムール貝に近い二枚貝です。

名前ゲルビリア・フォルベシアーナ
学名Gervillia forbesiana
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
笹の葉っぱのような長細い殻を持つ二枚貝です。有田層では、断片的なものはよく見つかります。殻の長さは約10㎝です。

名前ハボウキガイ属の一種
学名Pinna sp.
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
長細い三角形の殻を持つ二枚貝です。これの近縁な現生種は、潮干狩りなどをしているとたまに見つかることがあります。
*写真の白黒のスケールは一目盛り2㎝です。

名前ネズミノテガイ属の一種
学名Plicatula sp.
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
この標本は殻が溶けたあと、その模様が周りの岩の表面に残されたもの(印象化石)です。ネズミノテガイの殻の表面には放射状の肋があり、その肋の上には針状の突起があるのですが、この標本ではその様子がよくわかります。

名前ラステラム・カリナータム
学名Rastellum carinatum
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
寄贈大西哲朗氏
カキの仲間です。二枚の殻の合わせ目がギザギザになっていて、まるで牙をむいたワニの口にように見えます。

名前プテロトリゴニア・ポシリフォルミス
学名Pterotrigonia pocilliformis
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
三角貝の一種です。鳥のつばさのような形の殻で、その表面は太い肋で覆われています。
*写真の白黒のスケールは一目盛り2㎝です

名前レサトリックス属の一種
学名Resatrix sp.
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
レサトリックスは、現生種で言えば、ハマグリに近縁な絶滅種です。
ウニの化石

名前ヘテラステル属の一種
学名Heteraster sp.
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
寄贈中尾方香氏
ヘテラステルはブンブク類に属する絶滅種です。
現生のブンブク類は泥や砂の中にもぐって生息しています。殻の長径は約7㎝です。
植物の化石

名前ニルソニア属の一種
学名Nilssonia cf. densinervis
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
ニルソニアは、ソテツの仲間です。

名前ザミテス属?の一種
学名Zamites ? sp.
産地和歌山県有田郡湯浅町栖原
地層有田層
年代中生代白亜紀前期(約1億3000万年前)
ザミテスはソテツの仲間です。有田層は海底で形成された地層ですが、陸から運ばれてきたと考えられる植物の化石がときどき見つかります。
*写真の白黒のスケールは一目盛り2㎝です。