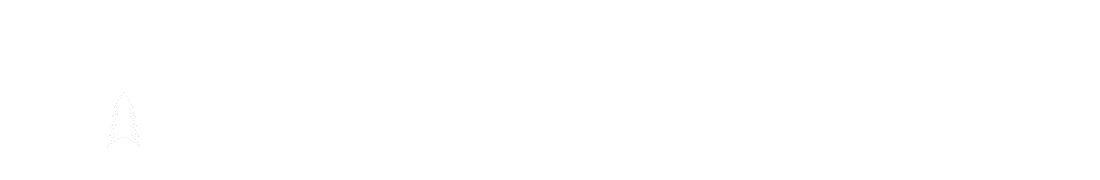紀州の鯊(ハゼ)Gobies in Kishu
30 ウキゴリ (浮鮴)
スズキ目ハゼ科ウキゴリ属

ウキゴリGymnogobius urotaeniaは国内では北海道から九州、屋久島(やくしま)まで、国外では千島列島(ちしまれっとう)、朝鮮半島(ちょうせんはんとう)に分布する体長12センチ程のハゼ科魚類です。ウキゴリは河口などの汽水域(きすいいき)から河川中流までの淡水域(たんすいいき)で、流れが緩(ゆる)く抽水(ちゅうすい)・沈水性植物(ちんすいせいしょくぶつ)が繁茂(はんも)するような場所に生息します。和歌山県では北部から南部にかけての河川やため池で確認されていますが、生息確認できた場所が少ないこと、生息に適した水辺環境が減っていることから和歌山県版レッドデータブックの準絶滅危惧種(じゅんぜつめつきぐしゅ)に指定されています。
ウキゴリは、両眼(りょうがん)の間隔(かんかく)が広いこと、第1背鰭(せびれ)後部に黒斑(こくはん)があること、尾鰭基底(おびれきてい)の黒斑は丸く、分枝(ぶんし)しないことで他のウキゴリ属(ぞく)と区別できます。ウキゴリの繁殖(はんしょく)は、早春のまだ水が冷たい時期に石の下にオスが巣穴(すあな)を掘ってメスを誘(さそ)い込んで行われます。卵(らん)は孵化(ふか)するまでオス親が保護(ほご)します。孵化した仔魚(しぎょ)は海へ下り、一般に両側回遊型(りょうそくかいゆうがた)の生活史(せいかつし)を送ると思われますが、琵琶湖(びわこ)や諏訪湖(すわこ)のように池や湖に陸封(りくふう)された個体群(こたいぐん)もあります。調べてみると、ちょっとしたため池にも陸封されているようで、「回遊」を考える上で興味深い魚です。春になると大量に幼魚(ようぎょ)が川へ遡上(そじょう)、あるいは湖岸(こがん)に接することから、昔から漁獲(ぎょかく)されてつくだ煮(に)などの材料となっています。
ウキゴリ属の仲間の多くは、ハゼの仲間では珍(めず)しく、成魚になっても中層(ちゅうそう)を遊泳(ゆうえい)します。本種も遊泳生活をするため、ウキゴリ(浮遊(ふゆう)するゴリ(ゴリはハゼの呼び名の一つ))という和名(わめい)が付いたものと思われます。しかし、同じ遊泳性ハゼでもサツキハゼParioglossus dotui(「紀州の鯊10」)やキヌバリPterogobius elapoides(「紀州の鯊25」)のような素早(すばや)さはなく、遊泳と言うよりは、浮遊という表現が正しい印象(いんしょう)を受けます。そんなウキゴリは、成魚でもスズキやロウニンアジのような高い遊泳力を持つ捕食者(ほしょくしゃ)や、ウナギやナマズなどの大型の肉食魚に襲(おそ)われる危険(きけん)があります。そのため隠(かく)れ家(が)となる抽水植物の生い茂る多い場所にすんでいるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。そして、わんどや浅い湿地(しっち)が減(へ)る昨今(さっこん)、多くの水辺の植物も姿(すがた)を消しつつあります。ウキゴリが続ける昔ながらの浮遊生活も脅(おびや)かされているのかもしれません。
(自然博物館だよりVol.27 No.1 ,2009年)