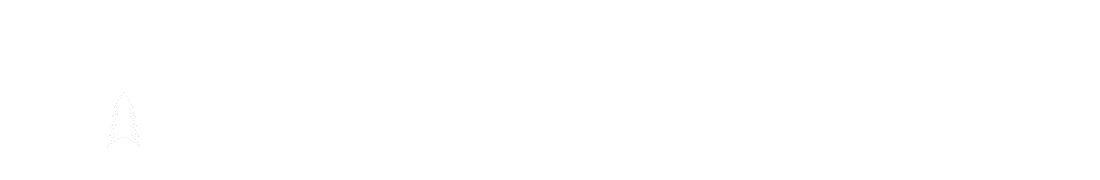紀州の鯊(ハゼ)Gobies in Kishu
31 ヒナハゼ (雛鯊)
スズキ目ハゼ科ヒナハゼ属

ヒナハゼRedigobius bikolanusは、日本海側では兵庫県、太平洋側では東京湾以南の沿岸汽水域から、河川下流域に普通に見られるヒナハゼ属のハゼです。ヒナハゼは名前のとおり体長は3㎝程度の小さなハゼで、他のハゼ科魚類の稚魚とゴマハゼPandaka sp.(紀州の鯊3 館だよりVo.19 No.1)と間違えられることもあります。特徴は、体側にある黒と白の模様で、「市松模様」にも例えられます。このことからヒナハゼは、「イチマツハゼ」とか、学名から「ビコールヒナハゼ」と呼ばれていた時期もあります。また、成熟したヒナハゼのオスは、第1背鰭が伸長し、口の後端は眼の後縁を越えるほど大きく裂けます。ヒナハゼは、淡水域から汽水域に生息していますが、特に抽水植物が生えていたり、水底に枯れ葉が積もったような小さな河川や止水域、コンクリート等で護岸されていないような用水路で見ることができます。ヒナハゼの詳しい産卵生態は不明な点がありますが、淡水域で成長すること、産卵は感潮域で行われること、孵化仔魚は海で成長して淡水域へ戻ってくることから、両側回遊型の生活史を送ると考えられます。
ヒナハゼは、主にカキ殻などの貝殻を産卵基質として利用しています。多くのハゼ類同様、ヒナハゼもオスが孵化するまで卵を保護しますが、必死に大きな口を開けて、自分よりも大きな魚やエビを威嚇する姿は健気です。ヒナハゼは水槽で飼育しやすい魚ですので、みなさんもこのような繁殖行動を観察するチャンスがあるかもしれませんね。
(自然博物館だよりVol.27 No.2, 2009年より改訂)