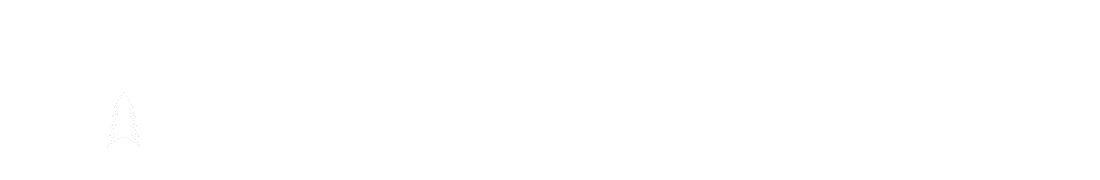紀州の鯊(ハゼ)Gobies in Kishu
47 アカオビシマハゼ (赤帯縞鯊)
スズキ目ハゼ科チチブ属

アカオビシマハゼTridentiger trigonocephalus (Gill, 1859)は体長10㎝ほどのチチブ属(ぞく)のハゼです。北海道から鹿児島県(かごしまけん)までの沿岸(えんがん)に広く分布し、内湾(ないわん)などの汽水域(きすいいき)に生息(せいそく)します。国外では朝鮮半島(ちょうせんはんとう)や中国沿岸部、台湾(たいわん)に分布しています。また、アメリカ合衆国(がっしゅうこく)のカルフォニア周辺やオーストラリアのシドニー周辺の水域にも外来魚として定着(ていちゃく)しているようです。
アカオビシマハゼは、頭部腹面に白点がないこと、胸鰭(むなびれ)最上軟条(さいじょうなんじょう)が遊離(ゆうり)することなどで近似種(きんじしゅ)のシモフリシマハゼT. bifasciatus Steindachner, 1881と区別できますが、両者が混在(こんざい)する地域では慣(な)れるまで区別が難しいでしょう。また、和名の由来となった「アカオビ」は赤褐色(せきかっしょく)の横帯(おうたい)として現れることもありますが現れない個体も多く、どちらかというと「シマハゼ」の名前の由来である頭部から尾柄部(びへいぶ)にかけての縞模様(しまもよう)の方が目立っています。体色変化も激(はげ)しいため、見た目にだまされやすいハゼのひとつです。
アカオビシマハゼは、和歌山県内の汽水域のいたるところで見られ、特に底質(ていしつ)が砂泥(さでい)で、カキ殻(がら)や礫(れき)の混じる場所に多く現れます。また、コンクリート護岸(ごがん)などの壁面(へきめん)にもくっついていることが多く、温かい時期には岸壁に付着した貝類や藻類(そうるい)の間を行き来する本種を観察できます。アカオビシマハゼの産卵もこのようなカキ殻などを利用して行われ、オスによって卵保護(らんほご)が行われます。孵化(ふか)した仔魚(しぎょ)はそのまま海中を浮遊(ふゆう)して、おおよそ一月半程度で底性生活(ていせいせいかつ)に入ります。
アカオビシマハゼがアメリカ大陸やオーストラリアに侵入(しんにゅう)できた理由としてタンカーのバラスト水*への混入が指摘(してき)されています。この仔稚魚(しちぎょ)の浮遊期間にバラスト水と共に紛(まぎ)れ込んだのでしょうか。しかし、暗いバラストタンク内で2,3ヶ月ものあいだ仔魚の餌(えさ)となるプランクトンが十分に得られる保証(ほしょう)もありません。私は、着底間近な個体や浮遊仔魚など様々な段階の仔稚魚が取り込まれ、タンク内である程度の淘汰(とうた)が起こり、生き残ったものが新天地に侵入したと考えるのですが、いかがでしょう。いずれにしても、連れて行かれたアカオビシマハゼも持ち込まれてしまったアメリカやオーストラリアの沿岸生物も迷惑(めいわく)でしょう。意図的でない人間の行為(こうい)が新たな外来生物を生み出さないように注意しなければいけません。
*タンカーなど大型輸送船(おおがたゆそうせん)が配送先で荷下ろし後、空荷で航行(こうこう)する際に、船体のバランスをとるため現地で船内タンク(バラストタンク)に大量に取り込む海水のこと。荷を積む際に、海へ排水(はいすい)される。
(自然博物館だよりVol.31 No.2,2013年)